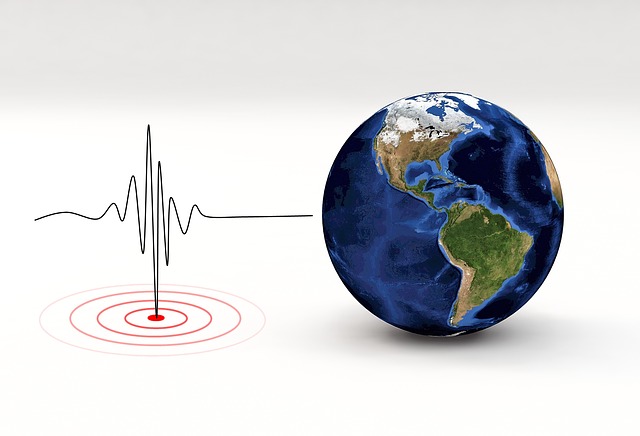利用用途は無限大!2D・3Dの構造躯体モデル
をダウンロードできるクラウドサービス「STRUCTUREBANK」
⇒ 【公式】https://www.structurebank.jpにアクセスして無料でデータをダウンロード
こんにちは!建築構造モデルデータダウンロードサービス「STRUCTUREBANK」の建築構造用語集 編集部です。
建築実務の中でも特に意匠設計に携わっている方は、一度は「仮定断面」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
普段から付き合いのある構造設計者に「このプランとボリュームで大体の部材断面を教えてほしい!」というときに、よく使いますね。
実務の中では当然のように仮定断面という言葉が飛び交いますが、一体どういうものかご存知でしょうか?
「要はまだ未計算の状態で仮の部材ってことでしょ?」とお考えではないですか?その通りです。
しかしどうしてわざわざ仮定の断面を構造設計者に出してもらう必要があるのでしょうか。
そこで今回は仮定断面を出す理由について解説いたします。
改めて「仮定断面」を説明しよう
仮定断面とは、構造計算を実際に行う前に、建物の用途や柱の入れ方などから、
だいたいの柱梁の断面を仮に設定することをいいます。
何のために仮定断面が必要なのか
仮定断面があることで、意匠設計者が基本計画を立てやすくなります。
例えば「さあどんなプランにしようかな」という段階では、まずおよその外形(ボリューム)を設定することになります。
斜線制限や高さ制限・意匠上の見え方などから徐々に形になってくれば、矩計などのもう少し細かいディテールも同時に考えなければなりません。
もしこの段階で「仮定断面」が無ければ、意匠設計者の経験で、柱や梁を配置していくことになります。
しかし時には、現実的ではない柱・梁の断面を設定してしまうことがあり、
実際に構造計算を依頼したときに「思ってたのと大きく違う部材配置になってしまった!」「プランが成り立たなくなるくらい架構が変わった…」ということになりかねません。
こういう時に、構造設計者の経験則による仮定断面があると、そういう事態を未然に防ぐことが出来るのです。
「仮定断面」は不毛な調整を省くためにめちゃくちゃ大事
構造設計者にとっても、建物の構造計画に当初から参画出来るので、
「プラン固まってるらしいけど、構造的に全然成り立ちそうにない…」というドツボに陥ることが無くなります。
仮定断面は、「ここが変わる可能性が高いですよ」とか「この部分が構造的に複雑なので、時間がかかりそうです」といったことを基本計画の段階で伝えることのできるコミュニケーションツールでもあるのです。
【設計者必見!!】構造設計の時間とコストを大幅に削減するクラウドサービス
STRUCTURE BANKは建築物の構造躯体モデルをダウンロードできるクラウドサービスです。
安全性を確認したリアルなモデルであるため、設計実務に利用することも、建築教育に利用することも
可能です。利用用途は無限大。
確かな安全性 :構造設計事務所が作成したモデルであるため、安全性はお墨付きです。
データの実用性:データを加工編集しても、実際の建築設計に利用することができます。
2D/3Dモデル :モデルは2Dのプランニングシート、3Dモデル(Revit、アーキトレンド)で提供しています。